| 割れ止め(製作)
左右が外れないように貼り付けますので、割れ止めの木目方向は図のようになります。 裏板の木目と平行に切り出してしまうと、割れ止めの 意味をなしません。 |
|
以前、失敗してほったらかしになっていたスプルース材(イングルマン。ハギ済み)から切り出しました。既に日焼け等により色むらがでてい るので、何の躊躇も無く切り出しました。 |
| 割れ止め(接着)
切り出した材のセンターをとり、裏板の接ぎ合わせの線にあわせて、貼り付けます。貼り付けにはタイトボンド?を使いました。塗りむらが ないようしっかり塗っています。 |
 接着剤が塗れたら、あて木をしてクランプで締めます。完全にあて木で覆ってしまうと、センターの印が見えませんので、端部は見えるように してあります。横に木目が通っているので、曲がって貼り付けてしまいやすいので注意します。今回は大きめのあて木をしましたので、あふれた接着剤をふき取ることができませんでした。硬化後、ノミで除去します。木部に傷をつけな いように丁寧に接着剤を切り取り、最後はサンディングで仕上げます。 接着剤が塗れたら、あて木をしてクランプで締めます。完全にあて木で覆ってしまうと、センターの印が見えませんので、端部は見えるように してあります。横に木目が通っているので、曲がって貼り付けてしまいやすいので注意します。今回は大きめのあて木をしましたので、あふれた接着剤をふき取ることができませんでした。硬化後、ノミで除去します。木部に傷をつけな いように丁寧に接着剤を切り取り、最後はサンディングで仕上げます。 |
| 割れ止め(整形)
中心を頂点に小さいカンナで三角を作っていきます。木目に垂直にカンナをあてるので、切れない刃物を使うと、えぐれたり欠けたりする危 険があります。 |
|
三角の頂点は、何かの拍子に工具等をぶつけて凹ませてしまったりしがちなので、以降はより慎重に扱うことが必要になります。 |
| 外形の切り落とし
外形に少し余白を持たせて切り落としますので、転写したラインを基準に、1cm程度余白をもたせて、切り取る線を引きました。 |
|
ノコギリでは曲線がうまく出ないので、小刀で角を落としています。別にしなくてもいい作業だと思いますが、気持ちだけ。 |
| 力木(切り出し)
切り出しの詳細については省略しますが、力木もテーブルソーで切り出します。私は刃のカバーを外していますが、刃で怪我する危険が増え るだけでなく、キックバック(材が自分のほうに飛んでくる)の危険もあります。怪我しても規定以外の使い方ですので、多分保険も利きません。 基本的には真似されないほうがいいと思いますし、カバーを外される場合は、完全自己責任です。 |
 切り出せれば、自動カンナを通して、厚み出しとともに、面を綺麗にします。厚みは10mm前後が一般的なように思います。 切り出せれば、自動カンナを通して、厚み出しとともに、面を綺麗にします。厚みは10mm前後が一般的なように思います。 |
| 力木(接着面の整形)
Rが足りないと、平面的で面白みのないギターになりますし、逆に付け過ぎると以降の作業(胴削り、バインディングの溝切り等)が難しく なりますし、将来的な故障(力木の割れや剥がれ)の原因になります。その辺りの見極めは、美しさ(あるいは個性)と機能を秤にかけた上での 製作者の勘ということになると思います。 |
|
また、目視や手で触った間隔で面が狂っているところがないか、なだらかな連続した曲面が出ているか等も確認します。面が出たら、サンド ペーパーで細かい凸凹を取ります。 |
| 割れ止めの除去
切り込みはしっかり裏板に到達するところまで入れておきます。 この直線がいい加減だと、力木が平行に並びませんので、もし失敗したら 必ず修正しておきます。 |
|
少しでも切り残しがあれば、そこが密着しないことになりますから、完全に密着するように綺麗にしておきます。 裏板の力木が外れると音の輪郭がぼやけると言われます。実際に、力木の外れたギターの裏板を手で押し、力木を密着させてやると、 音がどう変化するのかがよくわかります。 |
| 力木(接着)
接着の前に、割れ止めの溝が、緩すぎず、きつすぎず、また力木3本が綺麗に平行に並んでいるか、基本的には目視、目視だけで自信が無い 場合は、定規で、割れ止めのセンターとの直角や力木の幅の間隔を計って確認します。 |
|
クランプで締め終えたら、接着剤が乾くまでに、水を使い、絞り出した接着剤を拭き取り(流し取り)ます。力木の掃除には、私は基本的に 歯ブラシを使うことが多いです。 |
| 力木(整形)
|
|
面取りができれば、端部を薄くします。端部を薄くするのは、ブレースに力がかかったときそこから逃がすためで、薄くしておかないと ブレースが簡単に折れてしまうようです。 普段は50mmぐらい取るのですが、今回は胴の幅が狭いので、 |
|
|

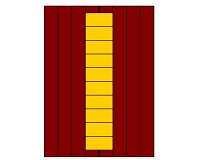 面が仕上がれば、割れ止めを接着します。割れ止め用に切り出された材も普通に販売されていますが、今回は板材から切り出します。
面が仕上がれば、割れ止めを接着します。割れ止め用に切り出された材も普通に販売されていますが、今回は板材から切り出します。
 割れ止めを貼ってしまうと、力木を配置する直線を引くのが少し面倒になります。割れ止めを貼る前に、ブレースの位置を落としておきました。 今回は難しいことは考えずに、均等に配置してみました。鉛筆で罫書く時は、最悪消せなくなる場合がありますので、サウンドホールから見て、力木の陰になって見えなくなるほうに線を引きます。 ちょっとしたことですが、接着作業が終わるたびにきっちりとあふれた接着剤を除去しておくとか、細かいことを積み重ねることで、綺麗な ギターに仕上がります。
割れ止めを貼ってしまうと、力木を配置する直線を引くのが少し面倒になります。割れ止めを貼る前に、ブレースの位置を落としておきました。 今回は難しいことは考えずに、均等に配置してみました。鉛筆で罫書く時は、最悪消せなくなる場合がありますので、サウンドホールから見て、力木の陰になって見えなくなるほうに線を引きます。 ちょっとしたことですが、接着作業が終わるたびにきっちりとあふれた接着剤を除去しておくとか、細かいことを積み重ねることで、綺麗な ギターに仕上がります。

 厚みを落すときに、外形の線が消えていますので、再度モールドを使い転写します。 板材には、節や入り皮があることがあります。 それらを上手に避けて取ります。今回の材料の場合は、避けようがないところに入り皮がありますので、それは諦めるとして、大きな節だけはボディにかからないように取 りました。
厚みを落すときに、外形の線が消えていますので、再度モールドを使い転写します。 板材には、節や入り皮があることがあります。 それらを上手に避けて取ります。今回の材料の場合は、避けようがないところに入り皮がありますので、それは諦めるとして、大きな節だけはボディにかからないように取 りました。 ノコギリで切り落とします。くびれ部分で木目に沿って割れてしまわないように、先にくびれ部分に切り込みを入れておきます。
ノコギリで切り落とします。くびれ部分で木目に沿って割れてしまわないように、先にくびれ部分に切り込みを入れておきます。 裏板の力木(ブレース)は、クラシックギターの場合はマホガニー、フォークギターの場合はスプルースが主流のように思います。ライニング材 は、スプルース、シダー等が主流のようです。個人的には材質にこだわりは無くて、ちょうど手元にホームセンターで選りすぐって購入し、寝かせ てあったシダーが、いい具合に乾燥してきましたので、それを使ってみたいと思います。力木は9mm×18mmが最終的に取れるようにしました。裏板の力木はクラシックギターでは3本、フォークギターでは4本が基本になっていると思 いますが、小ぶりなギターですので、今回は3本にしました。本数による利点は後述しますが、自分の考え方で決めて良い部分だと思います。
裏板の力木(ブレース)は、クラシックギターの場合はマホガニー、フォークギターの場合はスプルースが主流のように思います。ライニング材 は、スプルース、シダー等が主流のようです。個人的には材質にこだわりは無くて、ちょうど手元にホームセンターで選りすぐって購入し、寝かせ てあったシダーが、いい具合に乾燥してきましたので、それを使ってみたいと思います。力木は9mm×18mmが最終的に取れるようにしました。裏板の力木はクラシックギターでは3本、フォークギターでは4本が基本になっていると思 いますが、小ぶりなギターですので、今回は3本にしました。本数による利点は後述しますが、自分の考え方で決めて良い部分だと思います。 ブレース材が切りだせれば、接着面を加工していきます。まず裏板に合わせてみて、必要な長さ(板より少し長め)に切り落とします。長さが整えば裏板のブレースにRをつけます。Rはブレースによって違うし、私の場合、その時々で仕上がりが違うので、何ミリ落すとは言え ませんが、2mm~3mmぐらいでしょうか。まあ、結果合わせです。 作業は、小さめのカンナで円をイメージしながら、削って行きます。
ブレース材が切りだせれば、接着面を加工していきます。まず裏板に合わせてみて、必要な長さ(板より少し長め)に切り落とします。長さが整えば裏板のブレースにRをつけます。Rはブレースによって違うし、私の場合、その時々で仕上がりが違うので、何ミリ落すとは言え ませんが、2mm~3mmぐらいでしょうか。まあ、結果合わせです。 作業は、小さめのカンナで円をイメージしながら、削って行きます。 常に削った面が、側面と垂直になっているか、スコヤで確認しながら作業します。ギターを作るときは直角を出さないといけない場面が多いので、 スコヤは必需品です。
常に削った面が、側面と垂直になっているか、スコヤで確認しながら作業します。ギターを作るときは直角を出さないといけない場面が多いので、 スコヤは必需品です。 ブレース材が仕上がれば、次に貼り付けです。まず、ブレースが通る部分の割れ止めを外す部分を鉛筆で罫書きます。罫書きした線を正確に真っ直ぐにノミで切込みを入れます。ここで使っているノミは、幅が広く刃厚の薄い、ブレースを削るノミです。 綺麗な面で切るために、躊躇せず、一発で切ります。
ブレース材が仕上がれば、次に貼り付けです。まず、ブレースが通る部分の割れ止めを外す部分を鉛筆で罫書きます。罫書きした線を正確に真っ直ぐにノミで切込みを入れます。ここで使っているノミは、幅が広く刃厚の薄い、ブレースを削るノミです。 綺麗な面で切るために、躊躇せず、一発で切ります。 切り込みを入れられば、幅の細めのノミで取り除きます。ここで、取り残しがあると、そこが密着せず、ブレースと裏板に隙間が開きますので、 しっかり取り除いて接着面を出しておきます。
切り込みを入れられば、幅の細めのノミで取り除きます。ここで、取り残しがあると、そこが密着せず、ブレースと裏板に隙間が開きますので、 しっかり取り除いて接着面を出しておきます。 前述の通り、裏板のブレースはクラシックギター同様3本にしてあります。裏板の力木の本数が多いほど強度あるいは形状を維持する能力は 高くなりますが、本数が多いほど裏板のRを綺麗に連続させるのが難しくなります。力木の数だけでなく、ギター製作にはある程度の基準はありますが、それを大きく外さなければ製作者の考え(あるいは技量)で自由に作っても 問題ない部分が多くありますので、マニュアル通り作るのではなく、自分のやりやすいように変えていけばいいと思います。
前述の通り、裏板のブレースはクラシックギター同様3本にしてあります。裏板の力木の本数が多いほど強度あるいは形状を維持する能力は 高くなりますが、本数が多いほど裏板のRを綺麗に連続させるのが難しくなります。力木の数だけでなく、ギター製作にはある程度の基準はありますが、それを大きく外さなければ製作者の考え(あるいは技量)で自由に作っても 問題ない部分が多くありますので、マニュアル通り作るのではなく、自分のやりやすいように変えていけばいいと思います。 接着時は、接着剤で材がすべり、斜めについてしまうことが無いよう、常に位置を確認しながらクランプを締めて行きます。私は、ブレースは Rがついているので、外側に薄めでRに沿って曲がる板をあて木として使い、そのしなりで、満遍なく圧がかかるようにしています。力木の接着は、ゴーバークランプを使う人もいますし、それ以外の方法もいくつかあります。多分、私のやり方は一番よくないやり方だと思う のですが(裏板に「クランプの重み」+「締めすぎ」という過剰なストレスがかかる)、他の方法より楽なので採用しています。
接着時は、接着剤で材がすべり、斜めについてしまうことが無いよう、常に位置を確認しながらクランプを締めて行きます。私は、ブレースは Rがついているので、外側に薄めでRに沿って曲がる板をあて木として使い、そのしなりで、満遍なく圧がかかるようにしています。力木の接着は、ゴーバークランプを使う人もいますし、それ以外の方法もいくつかあります。多分、私のやり方は一番よくないやり方だと思う のですが(裏板に「クランプの重み」+「締めすぎ」という過剰なストレスがかかる)、他の方法より楽なので採用しています。 接着できれば、次にカンナで高さを調整し(今回はなんとなく16mmにしました)、高さがそろえば、今度はカンナを斜めにあて、少しずつ角度 をかえながらかけることで、上部を丸く仕上げます。気を付けるのは、逆目にはいってざっくりいかないよう、目の方向を常に意識することでしょうか。カンナでおおよそ仕上がれば、サンド ペーパーで細かい凸凹や傷を取ります。裏板の力木はサウンドホールから見えますので、できるだけ丁寧に仕上げた方がいいと思います。
接着できれば、次にカンナで高さを調整し(今回はなんとなく16mmにしました)、高さがそろえば、今度はカンナを斜めにあて、少しずつ角度 をかえながらかけることで、上部を丸く仕上げます。気を付けるのは、逆目にはいってざっくりいかないよう、目の方向を常に意識することでしょうか。カンナでおおよそ仕上がれば、サンド ペーパーで細かい凸凹や傷を取ります。裏板の力木はサウンドホールから見えますので、できるだけ丁寧に仕上げた方がいいと思います。 そんなに取ってしまうと不格好ですので、30mmに抑えます。幅広で刃の薄いノミで、 撥ね上げるように仕上げていきます。逆目にはいってざっくりいかないように注意します。 端部の厚みは5mmにしてみました。
そんなに取ってしまうと不格好ですので、30mmに抑えます。幅広で刃の薄いノミで、 撥ね上げるように仕上げていきます。逆目にはいってざっくりいかないように注意します。 端部の厚みは5mmにしてみました。 1項目あたり写真は2枚までとなんとなく決めていたのですが、裏板の最後なので、掟を破って3枚目に完成写真を載せておきます。
1項目あたり写真は2枚までとなんとなく決めていたのですが、裏板の最後なので、掟を破って3枚目に完成写真を載せておきます。